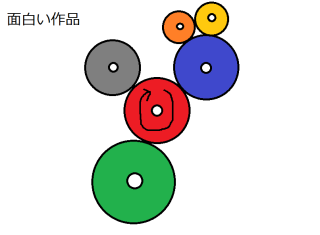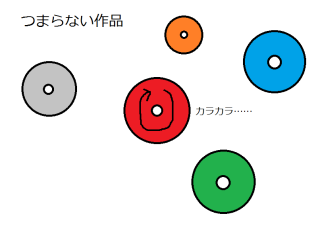3.ギミック理論
娯楽作品の面白さを決定する最大の要素とは一体何なのか?
一般的に言われるのが
「良くできたストーリー」や「魅力的なキャラクター」である。
ということは、良いストーリーやキャラを創造することが
作品を面白くする最善の策かというと、全くそうではない。
『1シ-ンに付き起こせる行動や出来事は1つだけ』であり
『その数は増やすことも減らすこともできない』という原則がある。
だから、いくら面白い展開や言動を用意しても
その数は増やすことができないので異常に効率が悪く。
単に「ストーリー」や「キャラ」を良くしたのでは、面白さには繋がりにくいのだ。
では、もっと効率が良く。面白さに繋がるものとは何か?
それが『リアクションの種類の多さ』なのである。
前にも述べたように
『1シーンで起こせるアクション(行動や出来事)は増やすことができない』
しかし、それに対する『リアクション』というのは、作り手次第で
いくらでも増やすことが可能なのだ。
当然、この「リアクションの数」こそが、面白さの客観的基準となる。
つまり、簡単に言ってしまうと面白いといわれる作品は、
このアクションに対するリアクションが常に豊富であり。
逆に、つまらないとされる作品は、
全体を通してリアクションが少ない傾向が強いのだ。
そして、作品のリアクションの多い少ないを左右するのが
「ストーリーのでき」や「キャラの魅力」ではなく。
その作品の持つ『ギミック構造』なのである。
ギミック構造とは、どんなものか。図で説明しよう。

赤い丸を「1シーンにつき1回転するモーターのギア」だとしよう。
(回転=アクションと考えてほしい)
このモーターが回転する時。面白い作品というのは
次のようになっている。
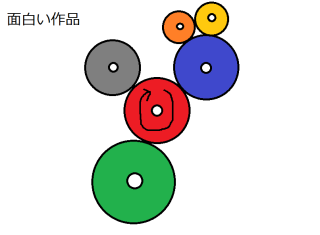
ご覧の通り、歯車がガッチリとかみ合い。
赤いモーターが1回転すると、他のギア達もしっかり動くのである。
では、つまらない作品だと、どうなるか?
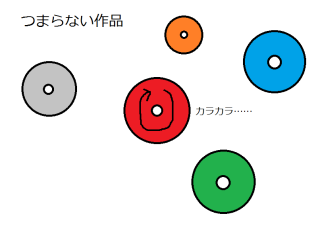
今度は歯車が全くかみ合っておらず。
主人公がアクションを起こしているのに、完全に空回りしている。
ストーリーは進んでいるが、何の盛り上がりもない
シラけた糞展開が想像できるのではないだろうか。
このようにストーリーを盛り上げることで最も重要なのは
ストーリーそのものやキャラクターの魅力ではなく。
「1アクション」に対して、沢山の「リアクション」が起こせるような
ストーリー展開やキャラクターの関係の配置。
つまり、それら『ギミック、構造』だということなのだ。
そして、この仮説には実に面白い点がある。
現実のモーターでは、多数のギアを噛ませると
その負荷によって、モーターの回転数は落ちてしまう。が、
創作物の原則においては
『1シーンにおけるアクション(回転)の数は、増えることも減ることもない』ため。
どんなに負荷を掛けてもモーターの回転(登場人物のアクション)は
1つから増えることも減ることもないため。
負荷を掛けければ掛けるほど得られるパワーは増えていくのだ。
これこそ、同じエンジン(制約)でありながら
面白さとして差が生まれる最大の原因なのである。
では、ようやく話を面白さの数値化に戻そう。
もうお気付きかと思うが面白さの数値である「tGP」とは
1アクションに対するリアクションの数によって算出される。
その方法はこうだ。
まず、映画でも漫画でもいいので、どこか1つのシーンを選び。
「受動態を使用せず」「アクションを具体的かつ簡潔に表し」
①「××が○○をしている」シーンと
シーンを定義する。
②そして、○○というアクションに対して
何種類のリアクションが起こったかを数える。
……以上、終了である。
この時、リアクションの種類が1つなら『1tGP』であり、2つなら『2tGP』
3つなら『3tGP』となり。この数値が高いほど
「その作品(のこのシーン)は、客観的にいって面白い」といえるのである。
そして、あなたがシナリオなり脚本なりを作っている時。
不安を感じたら、そのシーンを定義して「tGP」を算出し
もし、1tGPや0tGPしか無いなら、高いtGPが出せるよう
ギミック構造を作り直せばいいのである。
そのtGPによって、仮に問題が解決したとしたら
それは「世界の理不尽を1つ潰した」ことを意味し。
この世にとって、間違いなくプラスであるはずだ。
このように作品の出来を客観的な数値に直し
可視化してクオリティアップに役立てる。
これが私の考案した最先端の創作技法
『ギミック理論』である。
では、「創作無間地獄」に苦しむ罪無きドリーマーが
一人でも多く理不尽を打ち砕けることを祈りながら
これからはギミック理論を具体的な例を挙げつつ解説していこう。
4.何故スラムダンクは面白いか?に続く。
|